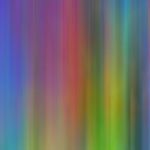さまざまな信仰をもつ全国各地の有名神社
「日本全国にある有名な神社について知りたい」
「神社本庁の歴史や所在地ってどこ?」
「伊勢神宮に一度は行ってみたい」
神社は我が国固有の信仰である神道に根ざすものですが、実際のところ信仰のあり方は祀られている神によって、あるいは鎮座する地域によって、大きな違いをもつことがあります。
たとえば祀られる神の種類で鳥居のかたちが微妙に違っていることがありますし、地域によっては本殿のような建物をもたずに拝殿から後背地にある神体山を直接参拝できるようになっていることもあります。
水辺や街なか、山の頂といった場所の違いも大きく、同じ名称ではありながら、このような多様性に支えられているのも我が国の神社の特色といえるでしょう。
神社本庁がどのような役割や活動を行っているのか、概要や取り組みについて紹介します。
→神社本庁 離脱した神社
皇室の祖先神として崇敬されている伊勢神宮
なかでも皇室の祖先神として崇敬されているのが伊勢神宮です。
かつては個人が私的な願いごとのために供え物をすることは禁止されていましたが、実際のところは伊勢御師の活動を通じてその信仰は全国各地の庶民層にまで広がっており、特に五街道が発達した江戸時代には伊勢参りも盛んになりました。
現在では誰でも自由に参拝ができるようになったことから、正月の初詣をはじめ年間を通じて多くの参拝客が訪れるようになっています。
それとともに、おかげ横丁やおはらい町など、参拝客向けにさまざまな土産物を売ったり、食事やデザートなどを提供する店舗も増え、観光地としてもにぎわいをみせています。
伊勢神宮の鳥居は白木でつくられており、笠木とよばれる部分が五角形をしているのが特色です。
全国に伊勢神宮の祭神である天照大神を分祀した神社は数多く存在しており、神明社という社号をもつことが多いといえます。
これらもやはり鳥居は伊勢神宮にならった神明鳥居です。
本社が滋賀県大津市にある日吉大社
日吉大社は本社が滋賀県大津市にあり、天台宗の総本山である比叡山延暦寺がここに拠点を定める以前から存在した山の地主神を祀っています。
この当時から比叡山を守護する神、また京都の鬼門にあたる方角を守護する神として敬われてきましたが、特に比叡山の勢力が増す中世になると神仏習合が進み、山王権現とよばれるようにもなりました。
そのため全国各地にある日吉社のほか、山王社と称するものもここからの分霊を祀ったものといえます。
日吉大社は有名な織田勢による比叡山焼き討ちによって焼失していますが、その後は豊臣・徳川政権によって復興が図られており、現在残っている建物の多くはこのときのものです。
西本宮や東本宮の本殿はそれぞれ国宝に指定されており、いまでも日吉造りとよばれる独特な様式を見ることができます。
日吉大社や各地の日吉社・山王社の鳥居も同様に独特であり、三角形の破風すなわち屋根が鳥居の上部に乗っており、全体は朱色に塗られているのがデフォルトです。
この形状も実は神仏習合のあらわれといわれています。
稲荷社の総本社である伏見稲荷大社
伏見稲荷大社は京都府伏見区の稲荷山に鎮座しており、全国に3万社ほどもあるといわれる稲荷社の総本社となっています。
山全体が神域となっており、麓のほうから山頂の本殿にまで続いている千本鳥居の風景は、京都を代表する風景としてよく知られ、写真などにもしばしば登場します。
この鳥居は全国各地の崇敬者によって寄進されたものですが、食べ物の神様である稲荷神を祀る神社の特色として、このように多くの赤い鳥居を重ねたものはよく見られます。
神のお使いをキツネとするところもユニークであり、稲荷社にはキツネの置物を多数奉納した狐塚が営まれていることがあります。
神仏習合が進んだ稲荷社のなかには、仏教的なダキニ天を祭神に祀っているものもあります。
これは我が国古来の稲荷神とはまた系統が異なり、神像には白狐にまたがる天女の姿で描かれています。
江戸時代には五穀豊穣はもちろんのこと、商売繁盛の御利益から商人の信仰も活発化し、そのために千本鳥居をはじめ莫大な奉納物を集めるようになりました。
全国の街角や個人の屋敷内などにも盛んに勧請され、さまざまな場所でお参りすることができます。
大分県宇佐市にある宇佐神宮
宇佐神宮は大分県宇佐市にあり、全国に4万社以上といわれる八幡社の総本社です。
上宮本殿に祀られている主神の八幡神は応神天皇のこととされ、それゆえに古くから皇室の崇敬を集めており、都の近くにも男山に石清水八幡宮が勧請されています。
山上には鮮やかな朱色に塗られたさまざまな建物があり、上宮本殿などは国宝に指定され、境内の全域にわたり国史跡となっています。
古代律令制の時代の地方官庁にあたる国府、あるいは国分寺の守護に勧請されたものが今に残っているケースも多く、これらは国府八幡宮などといわれます。
八幡神は源氏が信仰したことから武門の神としても知られ、鎌倉幕府が開かれた鎌倉の地にある鶴岡八幡宮なども、いまでも参拝客の絶えないところです。
神使は鳩とされていますので、境内には鳩が多いのも頷けます。
八幡宮の鳥居は笠木などの部分に反り返りがないのもポイントです。
まとめ
このように我が国には伊勢神宮・日吉大社・伏見稲荷大社・宇佐神宮などさまざまな異なる特色をもつ神社があり、それぞれ勧請というかたちで全国各地に多くの分社が鎮座しています。
したがって本社のみならず、それぞれの分社がある場所で独自の信仰をはぐくみ、さらなる多様性を生んだとみることができるでしょう。
最終更新日 2025年5月19日 by leshal